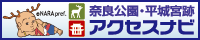参考コースからアレンジして頂けます!
希望の条件でコースを検索
ガイドコースのご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください。0742-27-9889お問合せ・申込受付 9:30 〜 16:00
お問い合わせフォーム フォームにご記入いただき、お問合せ下さい。1月の伝統行事
1月のおすすめコース
春日大社ゆったりコース
平城京の安泰と藤原氏の繁栄を願って造営された春日大社も今は初詣、お宮参りや七五三などで一般の信仰を集めています。基本コースに加え、夫婦大黒社をはじめ春日大社の摂社・末社のパワースポットを巡ります。
興福寺ゆったりコース
興福寺は藤原家の氏寺です。創建ははるか天智天皇の時代にさかのぼります。基本コースの東金堂・国宝館拝観と五重塔に加え、猿沢池、南円堂、三重塔、北円堂など興福寺境内をじっくり巡ります。(現在、五重塔は保存修理を実施しているため、素屋根で覆われその姿を見ることができなくなっています。)
今おすすめの企画ガイド
世界遺産(古都奈良の文化財)の東大寺・興福寺・春日大社・元興寺・薬師寺・唐招提寺・春日山原始林・平城宮跡を中心に奈良市内をガイドします。外国の方には英語でのガイドもいたします。
ガイドと歩くひと味ちがった奈良 実施予定
令和7年12月から令和8年4月までの「ガイドと歩くひと味ちがった奈良」実施予定の一覧です。個々の企画のコース詳細等が決まれば、赤丸印の番号でお知らせします。
<観光ボランティアガイドと歩く・なら> 東大寺 お水取りの秘密を探る
修二会(お水取り)行事が行われている東大寺の界隈に残る お水取りに関わる知られざる秘密を、ガイドと一緒に探りながら巡ります。
ボランティアガイドがご案内「鹿寄せと春日大社」
奈良公園飛火野(春日大社境内)で行われる「鹿寄せ」。ナチュラルホルンの音色を聞き、鹿たちが一斉に集まる様子は、奈良ならではの光景です。その後は世界遺産の春日大社境内をたっぷりご案内します。
<路地ぶら ならまち・きたまち2026共催企画>「路地ぶら ならまち・きたまち 2026」ガイドツアー
「ならまち・きたまち」エリアで、通常は予約が必要な寺院での特別拝観や御朱印がいただける冬の人気イベント「路地ぶら」今年は「お寺の案内」も「まち歩き」も楽しんでみませんか? ボランティアガイドが、地元ならではのお話でご案内します。
知って奈良 ウエルカムガイド
奈良市に転入される方、転入されて1年以内の方 ようこそ奈良市へ!「知って奈良 ウエルカムガイド」は、奈良市に転入された方対象に、市が実施しているウェルカムサービスです。 日本中で、この奈良市だけ! 三つのうちのご希望のコ […]

私たちについて
なら・観光ボランティアガイドの会「朱雀」とは
「なら大好き人間」が奈良の良さをもっと多くの人に知ってもらいたいという思いで、1997年(平成9年)7月に結成しました。「朱雀」は、なら・観光ボランティアガイドの会の愛称です。四神の1つで南の方角を守り、しあわせや繁栄を呼ぶと言われています。

ガイドの申込みはこちら
Tel. 0742-27-9889
受付時間 9:30 ~ 16:00
お役立ちコンテンツ
外部リンク(新規ページが開きます)
なら・観光ボランティアガイドの会「朱雀」へのアクセス
所在地
〒630-8228 奈良市上三条町23-4
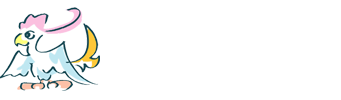









![ガイドと歩くひと味ちがった奈良 実施予定一覧 [令和7年12月 ~令和8年4月]](https://e-suzaku.net/gnr/wp-content/uploads/2025/10/ic_20251206-20260405_guide_ichiran_normal-300x187.jpg)
![<観光ボランティ アガイドと歩く・なら> 東大寺 お水取りの秘密を探る [令和8年3月8日(日)集合:09:00~09:30(順次出発)解散:12:30頃]](https://e-suzaku.net/gnr/wp-content/uploads/2026/01/ic_20260308_omizutorinohimitsu_anime-300x187.gif)
![ガイドと歩くひと味違った奈良 日本のピラミッドと幻の大寺院を巡る [令和8年3月28日(土)13:30~16:00]](https://e-suzaku.net/gnr/wp-content/uploads/2026/01/ic_20260328_pyramid_anime-300x187.gif)
![ボランティアガイドがご案内「鹿寄せと春日大社」[令和8年1月10日~令和8年2月28日 毎週土・日曜日(1月24・25日休)]](https://e-suzaku.net/gnr/wp-content/uploads/2026/01/ic_20260110-20260228_shikayose_normal_02-300x187.jpg)

![「奈良市」へ転入された方に 名勝・史跡の観光案内をプレゼント[知って奈良 ウエルカムガイド]](https://e-suzaku.net/gnr/wp-content/uploads/2023/07/ic_welcom_guide_01-300x187.jpg)