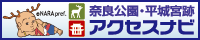一般の方用申込み
お一人様からお申込み頂けます
学校関係の方用申込み
修学旅行や遠足等、学校関係の方用申込み
Application in English
For your experience and pleasure in Nara
参考コースからアレンジして頂けます!
希望の条件でコースを検索
ガイドコースのご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください。0742-27-9889お問合せ・申込受付 9:30 〜 16:00
お問い合わせフォーム フォームにご記入いただき、お問合せ下さい。4月の伝統行事
4月のおすすめコース
桜花爛漫 佐保川から平城宮跡へ
JR「奈良駅」から、さくらと史跡を巡りながら、奈良のさくらを満喫するというコースをご紹介。春日山を源流として奈良市内を流れる佐保川は、知る人ぞ知る桜の名所です。
今おすすめの企画ガイド
世界遺産(古都奈良の文化財)の東大寺・興福寺・春日大社・元興寺・薬師寺・唐招提寺・春日山原始林・平城宮跡を中心に奈良市内をガイドします。外国の方には英語でのガイドもいたします。
養成講座説明会のご案内
私たち「NPO法人 なら・観光ボランティアガイドの会」は、観光客や修学旅行生に、奈良公園内をはじめ、奈良市内の寺社や文化財を案内している観光ボランティアガイドの会です。この度新会員を募集するにあたり、入会ご希望の方に向け […]
~25周年を迎えた世界遺産をもっと知ろう~ 世界遺産「古都奈良の文化財」25 の謎を解く
奈良市の世界遺産「古都奈良の文化財」に登録された社寺に秘められた謎を、 ガイドと一緒に解きながら、奈良公園の世界遺産を巡りませんか。
知って奈良 ウエルカムガイド
奈良市に転入される方、転入されて1年以内の方 ようこそ奈良市へ!「知って奈良 ウエルカムガイド」は、奈良市に転入された方対象に、市が実施しているウェルカムサービスです。 日本中で、この奈良市だけ! 三つのうちのご希望のコ […]

私たちについて
なら・観光ボランティアガイドの会「朱雀」とは
「なら大好き人間」が奈良の良さをもっと多くの人に知ってもらいたいという思いで、1997年(平成9年)7月に結成しました。「朱雀」は、なら・観光ボランティアガイドの会の愛称です。四神の1つで南の方角を守り、しあわせや繁栄を呼ぶと言われています。

ガイドの申込みはこちら
Tel. 0742-27-9889
受付時間 9:30 ~ 16:00
お役立ちコンテンツ
外部リンク(新規ページが開きます)
なら・観光ボランティアガイドの会「朱雀」へのアクセス
所在地
〒630-8228 奈良市上三条町23-4
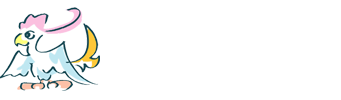









![第19期 新規会員募集 養成講座説明会のご案内[令和6年4月24日(水)午後1時30分~午後4時 於:]奈良市中部公民館 (奈良市上三条町23-4)](https://e-suzaku.net/gnr/wp-content/uploads/2024/03/ic_recruitment_2024_19th_anime_01-300x187.gif)
![~25周年を迎えた世界遺産をもっと知ろう~ 世界遺産「古都奈良の文化財」25 の謎を解く[4月6日(土) ~ 6月30日(日) 毎週 土・日曜日]](https://e-suzaku.net/gnr/wp-content/uploads/2024/03/ic_20240406-20240630_sekaiisan_normal_01-300x187.jpg)
![「奈良市」へ転入された方に 名勝・史跡の観光案内をプレゼント[知って奈良 ウエルカムガイド]](https://e-suzaku.net/gnr/wp-content/uploads/2023/07/ic_welcom_guide_01-300x187.jpg)