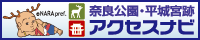一般の方用申込み
お一人様からお申込み頂けます
学校関係の方用申込み
修学旅行や遠足等、学校関係の方用申込み
Application in English
For your experience and pleasure in Nara
参考コースからアレンジして頂けます!
希望の条件でコースを検索
ガイドコースのご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください。0742-27-9889お問合せ・申込受付 9:30 〜 16:00
お問い合わせフォーム フォームにご記入いただき、お問合せ下さい。5月の伝統行事
5月のおすすめコース
興福寺ゆったりコース
興福寺は藤原家の氏寺です。創建ははるか天智天皇の時代にさかのぼります。基本コースの東金堂・国宝館拝観と五重塔に加え、猿沢池、南円堂、三重塔、北円堂など興福寺境内をじっくり巡ります。
奈良公園の四季(藤)
天平期の厳かな景観を楽しみ、鹿たちとのんびり過ごしながら、「藤の花」をめぐるコースをご紹介しましょう。藤原氏の氏寺の興福寺と氏神の春日大社では「藤」が大切に育てられています。
今おすすめの企画ガイド
世界遺産(古都奈良の文化財)の東大寺・興福寺・春日大社・元興寺・薬師寺・唐招提寺・春日山原始林・平城宮跡を中心に奈良市内をガイドします。外国の方には英語でのガイドもいたします。
~25周年を迎えた世界遺産をもっと知ろう~ 世界遺産「古都奈良の文化財」25 の謎を解く
奈良市の世界遺産「古都奈良の文化財」に登録された社寺に秘められた謎を、 ガイドと一緒に解きながら、奈良公園の世界遺産を巡りませんか。
知って奈良 ウエルカムガイド
奈良市に転入される方、転入されて1年以内の方 ようこそ奈良市へ!「知って奈良 ウエルカムガイド」は、奈良市に転入された方対象に、市が実施しているウェルカムサービスです。 日本中で、この奈良市だけ! 三つのうちのご希望のコ […]

私たちについて
なら・観光ボランティアガイドの会「朱雀」とは
「なら大好き人間」が奈良の良さをもっと多くの人に知ってもらいたいという思いで、1997年(平成9年)7月に結成しました。「朱雀」は、なら・観光ボランティアガイドの会の愛称です。四神の1つで南の方角を守り、しあわせや繁栄を呼ぶと言われています。

ガイドの申込みはこちら
Tel. 0742-27-9889
受付時間 9:30 ~ 16:00
お役立ちコンテンツ
外部リンク(新規ページが開きます)
なら・観光ボランティアガイドの会「朱雀」へのアクセス
所在地
〒630-8228 奈良市上三条町23-4
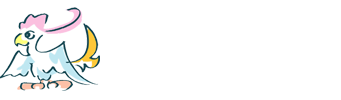









![~25周年を迎えた世界遺産をもっと知ろう~ 世界遺産「古都奈良の文化財」25 の謎を解く[4月6日(土) ~ 6月30日(日) 毎週 土・日曜日]](https://e-suzaku.net/gnr/wp-content/uploads/2024/03/ic_20240406-20240630_sekaiisan_normal_01-300x187.jpg)
![「奈良市」へ転入された方に 名勝・史跡の観光案内をプレゼント[知って奈良 ウエルカムガイド]](https://e-suzaku.net/gnr/wp-content/uploads/2023/07/ic_welcom_guide_01-300x187.jpg)